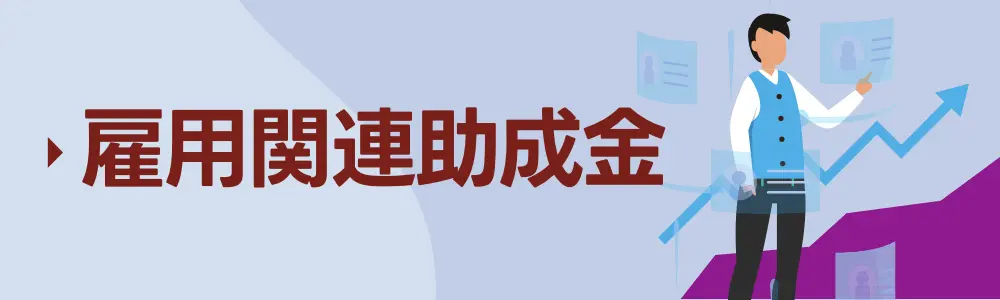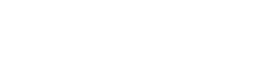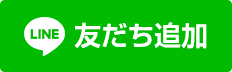ここ数年で一変したベースアップ・賃上げ傾向
数年前から、規模・業種を問わず非常に多くの企業が、大幅なベースアップや賃上げを行っている。当初は、大手企業や労働組合を有する企業が中心であったが、この2~3年については中堅企業や一部の中小企業なども大幅なベア・賃上げに踏み切っている。
このような高いベア・賃上げというのは、高度成長期からバブル経済期までは日本企業において当たり前のように実施されていたが、バブル崩壊後の平成大不況期以降は、制度上の定期昇給分による賃上げを除けば、大幅なベアや賃上げはほとんど実施されていなかった。
その結果、日本企業の賃金水準は、(近年の円安の影響を除いても)欧米諸国に大きく見劣りする結果となり、さらにはアジアの一部の国と比べても競争力が劣る水準となってしまった。
しかしながら、少子高齢化という社会構造的要因を背景とした人手不足が深刻化する中で、4~5年前から、大幅なベアや賃上げを実施する日本企業が増加しており、ベア率・賃上げ率も上昇の一途をたどっている。
併せて、少しでも優秀な新卒社員を獲得するべく、初任給の大幅な引き上げも相次いでおり、足元では30万円を超える初任給を提示する企業も珍しくはない。ほんの数年前までは、初任給が22万円、23万円を超えていれば、採用競争力で他社に劣ることはなかったが、最近では25万円以上の水準でなければ優秀な人材を引き付けることが難しい状況になっている。
大手企業ならでは、ベースアップ・賃上げの背景
上述の通り、ここ数年のベアや賃上げについては、企業の規模を問わず実施されているのがその特徴と言える。とは言え、大手企業と中小企業とでは、ベアや賃上げに対する“懐事情”は大きく異なっている。以下では、その点について、触れていきたい。
まずは大手企業について。
アフターコロナでは、多くの業種で業績好調な大手企業が増えているとは言え、この2~3年の大手企業のベア率や賃上げ率をみていると、「つい最近までの低い賃上げ時代は何だったのか?」と思わなくもない。結局の所、バブル崩壊後の平成大不況を経験したことによって、賃上げというイベントに対して「過度に委縮」していただけであり、大手企業に限って言えば「ない袖が振れなかった」わけではない、ということなのであろう。大企業における内部留保の水準が経年的に増え続けてきたという実態が、その証拠でもある。
それが、昨今の“超”のつく人手不足という状況になって、ようやく、実は原資に余裕のある大手企業を中心に、こぞって大幅なベアや賃上げが行われるようになった、・・・というのが現在の大手企業の実態であると個人的には認識している。
やむにやまれぬ、中小企業の実態
一方で、中小企業はどうか。
かつてに比べれば、受注先である大手企業等に対する単価交渉もしやすい環境・雰囲気になっているとは言え、現実には単価が引き上げられない、引き上げることができても微増にとどまる、といった中小・零細企業も決して少なくないと思われる。そのような中小・零細企業にとって、大手企業と同じような歩調・水準でベアや賃上げを実施することは、極めて難しいと言わざるを得ない。
しかしながら、賃金水準を全く引き上げない、もしくは引き上げてもわずかな上昇にとどめてしまえば、必要な人材の確保が余計に難しくなっていく現実もある。ゆえに、中小・零細企業は「ない袖を振る」というスタンスで、それなりのベア・賃上げを何とか行っているというのが、昨年・今年あたりの実態であるように思われる。ない袖でも無理して振らないと、すなわち、財務上のリスクテイクをしてでも賃上げを行わないと、結局は必要な人材を確保できずに、事業の縮小、さらには廃業という結果に陥ってしまうことが目に見えているからである。ここ数年、「人手不足倒産」が増えているという事実が、中小・零細企業の置かれている厳しい状況(進も地獄、退くも地獄)を分かりやすく物語っている。
中小企業における今後のベア・賃上げの要件とは?
大手企業と中小企業のそれぞれの“懐事情”を踏まえると、多くの中小企業については、早晩、少なくともこの数年間のような勢いでのベア・賃上げの実施は難しくなると思われる。大手企業のように、元から原資に余裕がない中で、かつ十分な生産性向上も伴わない状況での(大幅な)ベア・賃上げには、当然、限界がある。ただ、繰り返しになるが、ベアや賃上げができなければ、結果的には人手が足りずに経営や事業がシュリンクしていくことも避けられない。では、中小企業はどうすればよいのか?
正直な所、ウルトラCはない。早期に、ベアや賃上げの本来的な流れ、すなわち「生産性向上の結果としてのベア・賃上げ」というサイクルを作り出すことが必要である。生産性向上については、中小企業に限らず多くの日本企業にとって非常に苦手な部分ではあるが、そもそも、生産性向上を伴わないベアや賃上げには限界があるのである。
マクロ経済学の分野では、賃金について「効率賃金仮説」という経済理論がある。簡単に述べれば、「賃金水準を上げれば、労働者の労働効率が高まる」という考え方である。この理論・考え方については、否定的な捉え方もあるものの、個人的には「持って行き方次第」であると考えている。要は、単にベアや賃上げを実施するのではなく、「ベアや賃上げを、どのように生産性向上に結び付けていくのか?」という議論や検討がセットであるべき、ということである。
上記のような議論・検討と、その結果としての施策の推進について、会社として逃げずに愚直に取り組めるかどうかが、今後の中小企業の生き残りを左右することになると個人的には考えている。