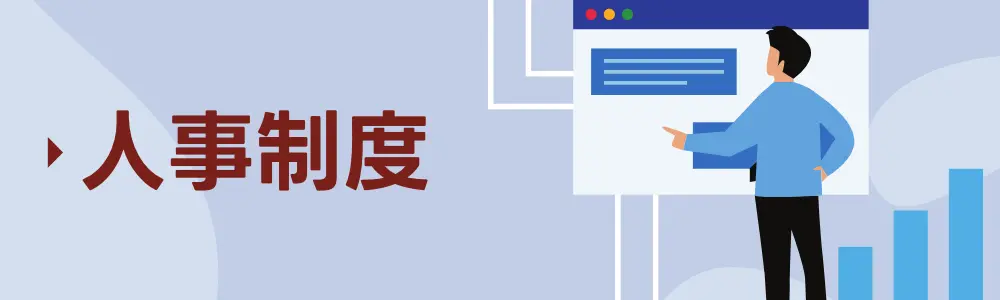目次
勤務間インターバル制度の義務化は見送りでも、なぜ企業は対策を急ぐべきなのか
2026年を目処に進められていた労働基準法の改正議論で、勤務間インターバル制度の「義務化」は見送られる公算が高まりました。しかし、これを「対策は不要」と捉えるのは早計です。
厚生労働省の有識者会議「労働基準関係法制研究会」の報告書では、当初、義務化が強く提言されていました。見送りの背景には政権の方針転換といった政治的な要因がありますが、従業員の健康確保と生産性向上という本質的な課題は未解決のままです。
労働力人口が減少する現代において、求職者から選ばれる企業になるためには、法的な義務の有無にかかわらず、自主的に休息時間を確保する仕組みづくりが不可欠です。
そもそも勤務間インターバル制度とは?目的と現状を再確認
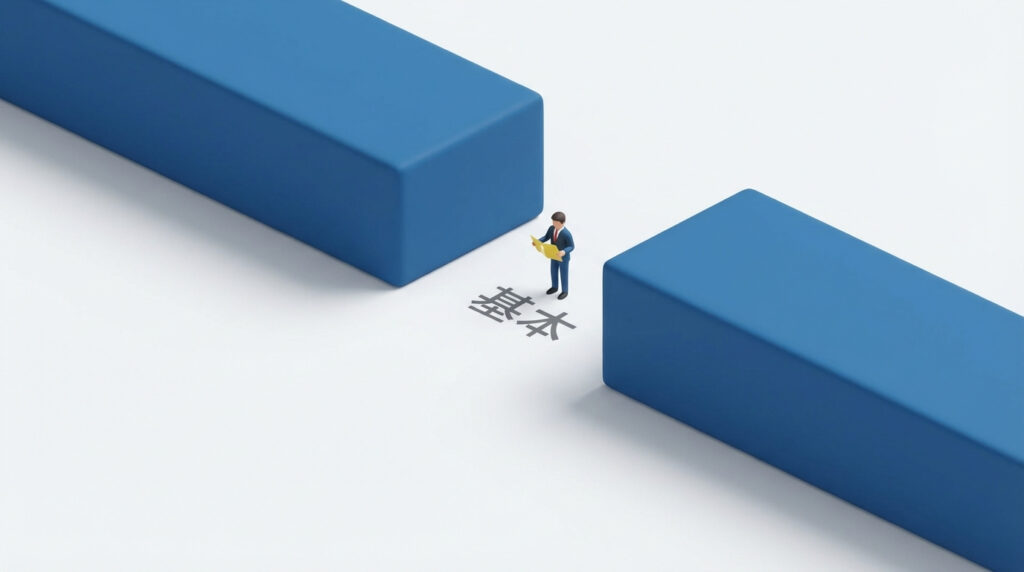
勤務間インターバル制度とは、1日の勤務終了後から翌日の出社までの間に、一定時間以上の「休息時間(インターバル)」を設ける仕組みを指します。
例えばインターバルを11時間と設定した場合、深夜23時に退社した従業員は、翌朝10時まで業務を開始させてはならず、休息を取らせる必要があります。これにより、睡眠時間やプライベートな時間を物理的に確保します。
制度の目的:従業員の健康確保と生産性向上・離職防止
この制度の主な目的は、過重労働の防止と従業員の健康確保にあります。十分な睡眠時間を確保することで、脳・心臓疾患のリスクを低減し、メンタルヘルス不調を防ぐ効果が期待できます。
企業側にも、従業員の疲労回復による集中力・生産性の向上や、ワークライフバランスの改善による離職率の低下といったメリットがあります。さらに「従業員を大切にする企業」として、採用ブランディングの強化にも繋がるでしょう。
現状の法的位置づけ:努力義務と低い導入率の実態
日本では2019年4月に施行された「働き方改革関連法」により、勤務間インターバル制度の導入が企業の「努力義務」と位置づけられました。しかし罰則規定がないこともあり、なかなか普及が進んでいないのが現状です。
厚生労働省の「令和6年就労条件総合調査」によると、勤務間インターバル制度を導入している企業の割合は、わずか5.7%にとどまっています。導入していない理由として最も多いのは「残業が少なく、制度を導入する必要性を感じないため」という回答でした。
義務化に向けた議論の経緯と「見送り」の最新動向

なぜ今回、義務化が見送られることになったのでしょうか。その背景には、義務化を推進する国際的な潮流とは対照的に、国内の政治的な事情が大きく影響しています。
EUの先行事例と国際的な流れ
世界に目を向けると、EU(欧州連合)ではすでに勤務間インターバルが義務化されています。1993年の「EU労働時間指令」によって、加盟国は原則として24時間につき最低連続11時間の休息期間を確保することが義務付けられました。
フランスやドイツなどの主要国では、この指令に基づいて国内法が整備されており、違反した企業には罰則が科されることもあります。日本における議論も、この国際基準である11時間のインターバルを意識して進められてきました。
国内での議論と労働基準法改正案「提出見送り」の背景
国内では、厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」が2024年末にまとめた報告書で、勤務間インターバル制度の義務化が提言されていました。しかし2025年に入ると、政府・与党内での調整が難航しました。
報道によると、規制強化を懸念する経済界への配慮や、政権が掲げる規制緩和の方針との整合性が取れなかったため、2026年の通常国会への改正法案提出は見送られる方向です。当面は現行の「努力義務」が継続される見通しですが、将来的な義務化の可能性が完全に消滅したわけではありません。
見送りでも油断禁物!休息不足がもたらす3つの企業リスク
義務化が見送られたからといって、従業員の休息不足を放置してよいわけではありません。適切なインターバルを確保しないことは、企業にとって重大なリスクになり得ます。
リスク1:安全配慮義務違反による法的責任
企業には労働契約法に基づき、従業員が安全に働けるよう配慮する「安全配慮義務」が課せられています。もし従業員が長時間労働や睡眠不足が原因で健康被害を受けた場合、企業が適切な休息を与えていなかったとして、損害賠償を請求されるリスクがあります。
過去の判例でも、十分な睡眠時間が確保できていなかったことが過労死や過労自殺の認定要因の一つとされています。そのため、インターバル制度を導入していないことが、間接的に企業の責任を問われる根拠になり得るのです。
リスク2:生産性の低下とヒューマンエラーの増加
睡眠不足は、脳のパフォーマンスを著しく低下させることが知られています。ある研究によると、睡眠不足の状態での作業能力は、酒気帯び運転と同程度まで低下するとも言われています。
集中力の欠如は、業務効率の低下を招くだけでなく、重大な事故やミス(ヒューマンエラー)を引き起こす原因にもなります。特に運送業や医療、製造現場などでは、一つのミスが人命に関わる大事故につながる恐れがあります。
リスク3:企業イメージの低下と採用競争力の喪失
近年、求職者は企業の「働きやすさ」を重視する傾向が強まっています。「残業が多い」「休みが取れない」といった口コミはSNSですぐに拡散され、いわゆるブラック企業というレッテルを貼られかねません。
逆に、勤務間インターバル制度を導入していることは、「従業員の健康を第一に考えるホワイト企業」であることの証明となり、優秀な人材を確保する上で強力なアピールポイントになります。
人事労務DXで推進!勤務間インターバル導入に向けた4ステップ

制度を導入するには、単にルールを決めるだけでなく、業務フローの見直しやシステムの活用が不可欠です。ここでは、制度導入における特に重要な4つのステップを解説します。
ステップ1:勤怠管理システムの活用で客観的な勤務実態を把握する
まずは、自社の現状を把握することから始めましょう。勤怠管理システムを活用し、従業員の退社時刻と翌日の出社時刻を正確に記録・分析します。
どの部署で、どの程度の頻度でインターバルが不足しているかを可視化し、対策が必要な箇所を特定します。その際、手書きや自己申告ではなく、客観的なログデータを用いることが重要です。
ステップ2:就業規則を見直し、社内ルールを明確化する
次に、就業規則に勤務間インターバル制度に関する規定を盛り込みます。具体的には、インターバルの時間(9時間、11時間など)、対象となる従業員の範囲、適用除外となるケースなどを明記する必要があります。
また、インターバルを確保するために始業時刻を繰り下げた場合、その時間を労働時間とみなすか、あるいは給与から控除するかといった賃金の取り扱いについても、あらかじめ定めておく必要があります。
ステップ3:業務フローやシフト体制を抜本的に見直す
制度を形骸化させないためには、業務そのものの見直しが欠かせません。特定の個人に業務が集中しないよう平準化を図ったり、シフト制の場合は勤務パターンを見直したりといった対策が必要です。
DXツールを活用して業務効率化を進め、残業時間そのものを削減することも、インターバルを確保するための根本的な解決策となります。
ステップ4:働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)を活用する
中小企業の場合は、厚生労働省の「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」を活用できます。この助成金は、新たに制度を導入したり、既存の制度を拡充したりする企業に対し、経費の一部を助成するものです。
労務管理用ソフトウェアや、労働能率を上げるための設備の導入費用、外部専門家によるコンサルティング費用などが対象です。2025年度(令和7年度)も継続して実施される見込みのため、資金面のサポートとして積極的に活用しましょう。
【Q&A】勤務間インターバル制度に関するよくある質問
最後に、制度導入にあたって人事担当者からよく寄せられる質問とその回答をご紹介します。
Q1. インターバル時間は何時間に設定すれば良いですか?
法律上の定めはありませんが、EU指令の基準である「11時間」が理想とされています。ただし、いきなり11時間を確保するのが難しい場合は、まず「9時間」からスタートし、段階的に時間を延ばしていく方法も有効です。
助成金の要件でも「9時間以上」や「11時間以上」といった区分が設けられています。自社の実態に合わせて無理のない範囲で設定することが、制度を定着させる鍵となります。
Q2. パート・アルバイトや管理監督者も対象になりますか?
制度の対象者は企業が任意で決められますが、健康管理の観点からは、雇用形態にかかわらず全従業員を対象とすることが望ましいでしょう。
特に管理監督者は労働時間規制の対象外となるため、長時間労働に陥りがちです。そのため安全配慮義務の観点からも、管理監督者を含めてインターバル制度を適用する企業が増えています。
Q3. 突発的なトラブルでインターバルを確保できない場合はどうすれば良いですか?
災害やシステム障害への対応といった、やむを得ない事情がある場合に備え、就業規則に「適用除外」や「特例」の規定を設けておくことが可能です。
ただし、例外を安易に認めると制度が形骸化する恐れがあります。「どのようなケースが該当するか」を具体的に定義し、例外を適用した場合は事後報告を義務付けるなど、厳格な運用ルールを定めておくことが重要です。
勤務間インターバル制度の義務化に備え、企業の競争力を高めよう
勤務間インターバル制度の義務化は見送られましたが、従業員の健康を守り、持続可能な組織を作る上で欠かせない仕組みです。法的な強制力を待つのではなく、助成金やDXツールを賢く活用しながら自社に合った形で導入を進めることが、結果として企業の競争力強化につながります。